フラワーレメディに使用されている植物にはそれぞれ個性があり、異なる作用・チカラを持っています。それを理解するには、まずは植物と向き合うことが大切です。そして植物を通して、私達は様々なことを学び、忘れかけていた事や思いもよらない様なひらめき、気づきに驚かされることと思います。
38種類のレメディには、湿地や水辺を好む植物がいくつか含まれています。
水辺周辺で生育する植物と草原や里山などの陸地に生育する植物とでは、形態に大きな違いが見られます。水辺の植物は水分を効率的に吸収・利用するため根や茎が発達していたり、細かく切れ込んだ葉を持つことで、水流による抵抗を減らし光を効率的に吸収できる構造を持つ等々、バッチ博士はその点も詳細に観察し、それぞれの植物が持つ癒しのチカラに気づき、レメディを作成しました。
ウォーターバイオレット(Hottonia palustris)は、水生植物として水中や湿地で生育するために様々な工夫をしています。例えば、ガス交換を行うための気孔(二酸化炭素を取り入れて、酸素を吐き出すための穴です)が葉の上面(表面)にあることで、水面に浮かぶ葉が効率的に光合成を行うことが可能になります。
(^^♪ 植物の気孔は、効率を考えて葉の表面と裏面にまんべんなく分散していたり、裏面だけというのが一般的です。
また根だけでなく葉からも養分を吸収でき、水質を浄化する役割も果たしています。このように長い時間を経て、ウォーターバイオレットは水中で生き抜くための適応力を身につけたのです。
ウォーターバイオレット・インパチェンス・ミムラスなど、水辺に暮らす植物のレメディの使い分け等につきましてはセミナーで一緒にご説明させて頂きます。
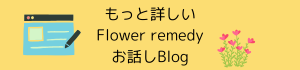 もっと詳しいウォーターバイオレットのご紹介ページはコチラです。
もっと詳しいウォーターバイオレットのご紹介ページはコチラです。
■□■…………………………………………………………………………………
♪ フラワーレメディのご使用方法に関しましては、
こちらのページをご覧ください。
…………………………………………………………………………………■□■




